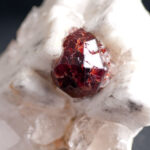コンコルドの開発から退役まで
この記事は執筆されてから1年が経過しています。

コンコルド(Concorde)はイギリスにあった「ブリティッシュ・エアクラフト・コーポレーション」とフランスにあった「シュド・アビアシオン」が共同で開発したマッハ2(時速2,170km)で飛行可能な超音速旅客機です。1960年代に開発が始まり、
1976年に商用運航が開始され、2003年10月に商用運航が終了した2024時点で商用運航された唯一の超音速旅客機です。
人類が音速を越えるまで
1930年代頃、各国で軍用機の速度を飛躍的に高める研究が行われていましたが、レシプロエンジンでは時速700km程度が限界でした。1940年代に入るとジェットエンジンが開発され、音速飛行が現実味を帯びてきました。
試験機が音速を超えた途端に操縦桿が操作できなくなったり、空中分解する事故が発生するなど、開発は危険と隣り合わせでした。
しかし、1947年にアメリカ空軍のテストパイロットだったチャック・イェーガーによって人類はついに音速の壁を突破することに成功します。1947年10月14日、NACA(現在のNASA)の試験機「X-1」に搭乗し、当初想定されていた衝撃波による振動もなくあっさりと音速飛行を実現しました。
人類が音速飛行に挑戦したエピソードは物語の都合上、一部にフィクションが含まれていますが、1983年に公開された映画「ライトスタッフ」で詳しく描かれています。
コンコルドが開発された背景
1950年代に入ると、アメリカを中心とした西側諸国とソ連を中心とした東側諸国は対立し、冷戦時代に突入し、核戦争の脅威が高まりました。その結果、アメリカとソ連は戦争に備えて兵器の強化を目的に「軍備拡張競争」を繰り広げました。
その結果、様々な技術分野での競争が活発化することになり、航空機、戦車などの兵器が飛躍的に進化したとされています。
そういう開発機運の中で、当時、独自に超音速機の研究をしていたイギリスとフランスが共同で開発する方針に転換した結果、誕生したのがコンコルドでした。
商用運航後も問題が山積み
1969年に初飛行を果たし、その後、技術的課題、政治的課題など数多くの課題に直面したものの、開発が続けられ、1976年にブリティッシュ・エアウェイズとエールフランスによって商用運行が開始されました。
しかし、その後のコンコルドを取り巻く世界情勢は決して明るいものではありませんでした。
コンコルドが音速飛行を行うとNOx(窒素酸化物)が排出されてオゾン層を破壊する可能性が科学的に示唆されました。それによって国際的な環境政策が議論になる中で、コンコルドの国際路線への拡大が阻害されたと考えられます。
また、1970年代中頃に人工的に作り出されたフロンガス(クロロフルオロカーボン類)がオゾン層を破壊する可能性が指摘されたことで、超音速飛行を含む航空業界を取り巻く環境がより厳しくなったと考えられます。
環境問題に加えて、コンコルドは高速飛行時にはアフターバーナーを使用するため多くの燃料を消費しました。
ボーイング747とコンコルドがニューヨーク、ロンドン間を飛行した場合、ボーイング747がより多くの燃料を消費します。しかし、ボーイング747は400人以上の乗客と貨物を運ぶ能力を持っていますが、コンコルドは最大でも128人しか運べません。
そのため、コンコルドの燃料消費量は非常に悪く、運用コストの高さが際立っています。
また、1970年代にはオイルショックが発生し、原油価格の高騰によりコンコルドの燃料消費量はさらに悪化したと考えられます。
つまり、
- 巡航速度: マッハ2.04 / ボーイング747-100(初期型)の巡航速度: マッハ0.84
- 最大乗客数: 128名 / ボーイング747-100(初期型)の最大乗客数: 452名
- 最大航続距離: 約7,200km / ボーイング747-100(初期型)の最大航続距離: 約9,800km
と、ボーイング747-100(初期型)と比べて、巡航速度以外は燃料消費量が悪く、運用コストが非常に悪い航空機でした。
また、開発当初は様々な航空会社から発注があったものの、ソニックブームによる騒音、1970年代からの問題視され始めたオゾン層の破壊などの環境問題、オイルショックの発生によりキャンセルが相次ぎ、試験機、先行量産機、量産機を含めて20機しか製造されなかったことに加えて、世界的に大量輸送、効率化、低コスト化に転換したことも大きく影響したと考えられます。
フランスでの墜落事故
2000年7月25日にエールフランス社のコンコルドが離陸直後のエンジン火災により墜落しました。
長期間の調査を経て2001年11月7日に運行の再開が認められたものの、直前の9月11日にアメリカ同時多発テロ事件が発生したことで、世界的に航空業界全体で需要が著しく低迷しました。
その結果、収益性の改善が望めなかったことを受け、2003年5月から11月にかけて、コンコルドの商用運航が終了し、全機が退役しました。
失敗例の象徴へ
コンコルドは開発から商用運航までに莫大な資金が投入され、商業的な成功が曖昧なまま、商用運航が開始され、騒音、環境問題の対応、オイルショックの発生、燃料消費量、運用コストが改善できないまま、全機が退役しました。
超音速旅客機の開発は非常に困難を極め、1960年代にボーイング社は「ボーイング2707」と呼ばれる超音速旅客機の開発に着手しましたが、実物大モックアップのみが製造され、原型試作機の製造に着手していたものの原型試作機が完成する前に計画が中止されました。
ソ連のツポレフ設計局でも「Tu-144」が開発、製造、運用されましたが、1977年に商用運航を開始しましたが、1978年に商用運航が中止されています。
コンコルドの開発、全機引退までの経緯から、投資や事業の継続が損失の拡大につながると分かっていても、これまでに費やした様々な努力、多額の資金、莫大な時間などを惜しむことで損切りができない心理現象を「コンコルド効果」と呼び、失敗例の象徴とされています。
短期的に見ると、コンコルドの開発から商用運航、退役までに多くの失敗があったように見えますが、コンコルドの開発で得られた技術は、その後の空力学と材料科学、超音速飛行の技術、航空技術や製造プロセスに様々な影響を与えていると考えられます。
そのため、長期的に見ると、今後登場する超音速旅客機、無人航空機の開発に何かしらの影響を与えたと考えることもできます。また、コンコルドの開発での失敗が次の新型航空機の開発に生かされている可能性も否定できません。